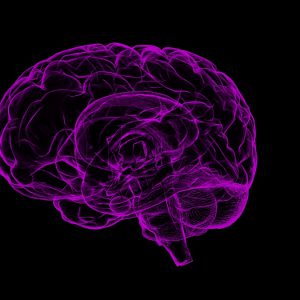移植外科とは?対象となる疾患や移植内科や内分泌外科との違いを簡単に紹介

移植外科とは、臓器移植に関する外科診療を行う診療科です。
慢性腎不全の根本的な治療である腎移植を中心に、透析で必要なシャント手術やシャントトラブルの治療、移植患者へのフォローアップなどを行います。
そこで、移植外科について、対象となる疾患、移植内科や内分泌外科との違いを簡単に紹介します。
移植外科とは
移植外科とは、慢性腎不全などの慢性腎臓病の患者への腎代替療法の外科手術と、術後のフォローアップを担当する診療科です。
肝硬変や急性肝不全などの末期肝疾患に対して、安全に肝移植治療に対応し、脳死下での小腸・膵臓移植を行います。
移植外科の対象疾患
移植外科で対応する診療として、以下が挙げられます。
・腎移植
・肝移植
・膵臓移植
・その他臓器移植
・移植後の患者の管理
・ドナーの健康管理
・透析患者に対するシャント手術
・移植に関連する合併症の治療
など
そのため、具体的な対象となる疾患は以下のとおりです。
・肝硬変(B型肝炎・C型肝炎・アルコール性・自己免疫性・原因不明など)
・胆汁うっ滞性疾患(原発性胆汁性胆管炎・原発性硬化性胆管炎・胆道閉鎖症など)
・急性肝不全(ウイルス性・薬剤性・原因不明など)
・代謝異常症(ウィルソン病・尿素サイクル異常症・家族性アミロイドポリニューロパチーなど)
・腫瘍(肝細胞癌など)
・血管疾患(バッドキアリ症候群など)
移植内科との違い
移植内科とは、腎臓移植や膵臓移植など、臓器移植が専門の内科です。
移植手術前後の移植された臓器機能維持に向けた治療を行う診療科であり、腎臓移植を希望する患者の窓口となります。
移植手術を行うまでの準備はもちろんのこと、移植後には長期的なフォローアップを実施します。
移植外科と移植内科は移植医療に携わる診療科であることは共通しているものの、担う役割と治療方法は異なります。
移植外科は、腎臓移植や膵臓移植などの臓器移植を外科手術で対応する診療科であるのに対し、移植内科は移植後の患者の全身管理やケアなどの内科的治療に対応します。
内分泌外科との違い
内分泌外科とは、甲状腺・副甲状腺・副腎などの内分泌臓器と乳腺・唾液腺などに発生する腫瘍性疾患、さらにホルモン分泌異常を伴う疾患が専門の診療科です。
内分泌外科と移植外科は外科の一分野であることは共通していますが、専門の疾患や治療法は異なります。
まず、内分泌外科は甲状腺・副甲状腺・副腎などの内分泌臓器とそれらに関係する疾患が専門であるのに対し、移植外科は臓器移植や移植後の管理やケアが専門であることが違いです。