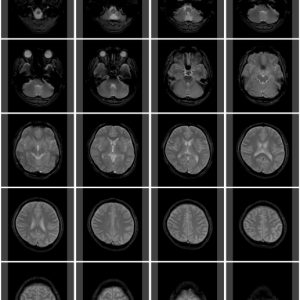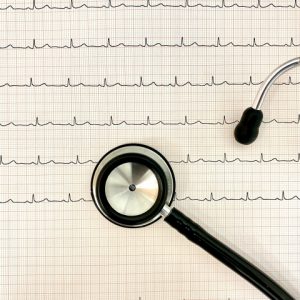肝・胆・膵外科とは?対象となる疾患や肝・胆・膵内科との違いを紹介

肝・胆・膵外科とは、肝臓・胆道(胆嚢・胆管)・膵臓に関する外科的疾患を専門とした診療科です。
消化・吸収・解毒・老廃物の処理など、生命を維持する上で重要な役割を担います。
先に挙げた臓器のがん(肝臓がん・胆道がん・膵臓がん)などや、胆石症・膵炎などの良性疾患について、外科治療を行う診療科です。
そこで、肝・胆・膵外科について、対象となる疾患や肝・胆・膵内科との違いを紹介します。
肝・胆・膵外科とは
肝・胆・膵外科とは、肝臓・胆嚢・胆管・膵臓などの消化器系の臓器が専門の外科です。
各臓器に発生する悪性腫瘍や、その他疾患に対する手術治療を行います。
肝胆膵領域の手術は難易度が高く、専門的な知識や技術を求められます。
肝胆膵は、肝臓・胆道(胆嚢・胆管・十二指腸乳頭)・膵臓領域を総称した呼称です。
それぞれの臓器は胃や大腸などのように、食べたものが通過する消化管ではありません。
ただし、消化・吸収・解毒・不要物の処理など、人が生命を維持する上で欠かせない役割を担います。
肝胆膵外科では、生命維持に重要な部位といえる肝胆膵の領域にできるがんの外科手術を専門とします。
腹部の深い位置にある肝胆膵領域は出血しやすい部分でもあるため、正しい診断と正確で安全な切除が必要です。
肝・胆・膵外科の対象疾患
肝・胆・膵外科の対象疾患で対象とするのは、肝がん・胆道(胆のう・胆管)がん・膵がんに対する肝切除・膵切除などの外科治療です。
診断・治療において高い専門性が求められることと、正しい診断と正確さが求められます。
肝臓・胆道・膵臓は血管や臓器が複雑に配置された領域に存在するため、血管や臓器は傷つけずにがんを切除しなければなりません。
手術後の生活に支障をきたすことなく手術を行うためにも、高度の技術が必要です。
どこにがんがあり、どこまで広がっているか、周辺の血管はどのように走っているかなどの正しい見極めが必要であり、高い経験と技量が求められます。
肝・胆・膵内科との違い
肝臓・胆道・膵臓のがんは、一般的に悪性度が高いことが多く、治療困難ながんに分類されます。
肝・胆・膵内科はでは、これらの部位にできたがんに対する内科治療を行い、標準治療だけでなく新たな治療の提供や開発を積極的に行います。
肝・胆・膵外科と肝・胆・膵内科はどちらも肝臓・胆道・膵臓の疾患を扱うことは共通していますが、外科は手術を行うのに対し、内科は薬物療法や内視鏡治療などをメインとする点に違いがあります。