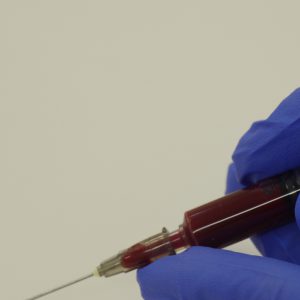胆管ステントとは?入れる理由や留置期間・詰まると見られる症状を解説

胆管ステントの治療とは、胆管の閉塞を解除し、胆汁の流れを改善するため治療方法です。
胆管の閉塞を開通させる目的で、網目状構造の金属製の筒または樹脂製チューブが胆管ステントです。
胆管ステントを留置することで、正常に胆汁が流れる経路が確保でき、胆管内からの胆汁を体外へ出すためチューブを外すことができます。
そこで、胆管ステントについて、入れる理由や留置期間、詰まると見られる症状を解説します。
胆管にステントを入れる理由
胆管ステントは、胆管の閉塞部位に入れることで、胆汁の流れを改善することを目的とします。
がん・結石・急性胆管炎などが原因で、胆管や膵管に狭窄ができると、消化液の流れがよどむため細菌感染が発生しやすくなります。
閉塞した胆管を放置すると、胆汁が胆のうに溜まれば黄疸を起こし、感染症で生命に危機を及ぼす恐れも否定できません。
そのために、胆管ステントを胆管等に挿入し、消化液の流れを回復させることが必要です。
胆管ステントの留置期間
胆管ステントの留置期間は、管に使用されている素材によって異なります。
たとえば、プラスチック製のステントであれば2~3か月程度、金属製のステントは6か月程度で閉塞すると考えられるため、交換が必要です。
金属製のステントは、プラスチック製よりも径が太く、閉塞リスクは低めではあるものの、必ずしも半年持つと言い切れません。
6か月よりも短くなる場合もあれば、長くなることもあるため、定期的な検査での確認が必要です。
閉塞した場合は、ステントの入れ替えを行うか、ステントを追加することなどが必要になります。
なお、ステント交換は内視鏡や経皮処置で行いますが、皮膚から針を刺す処置よる危険性もゼロとはいえません。
そのため、患者の状況によってはステントを留置したままにすることもありますが、経験の多い医師が行えばトラブルは少なめといえます。
胆管ステントが詰まると見られる症状
胆管ステントは、胆管に留置することで、胆汁の流れを保ちます。
そのため、ステントが詰まれば胆汁の流れを止めるため、黄疸・発熱・腹痛などの症状を起こします。
内視鏡処置や経皮的処置を行い、ステント交換することが必要であるため、症状が見られたときはすぐに医療機関を受診してください。
また、胆管ステントが抜けた場合も、黄疸・発熱・腹痛の症状が出るため、素材や状況によって抜去や再挿入などの処置が必要です。