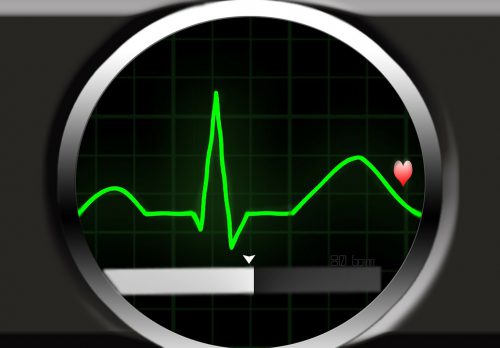ビデオ軟性血管鏡とは?特徴や内視鏡検査の方法を簡単に紹介
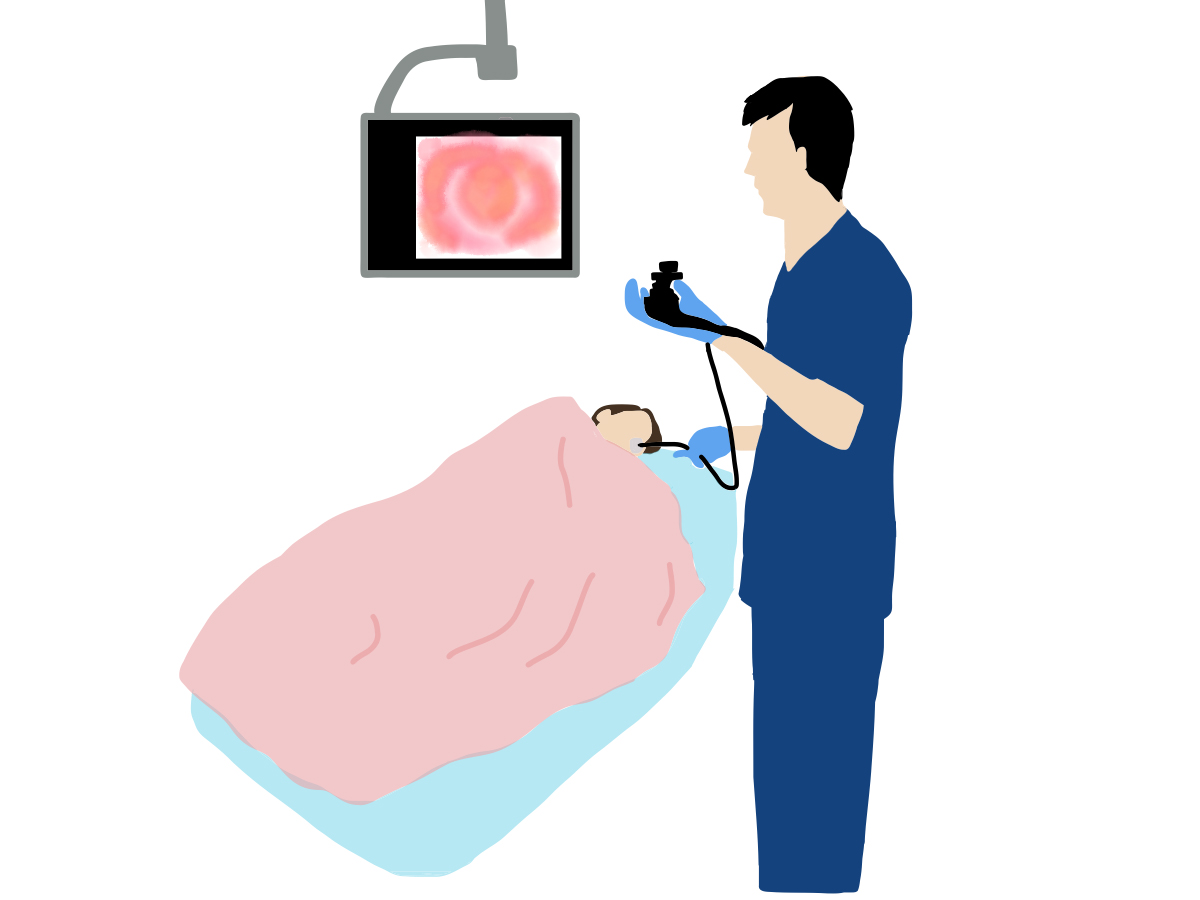
ビデオ軟性血管鏡とは、静脈または動脈の管腔を、観察・診断・治療するときに使う内視鏡です。
経皮的に挿入しますが、本品はビデオスコープであり、電荷結合素子(CCD)チップなどにより画像が供給されます。
主に内視鏡検査で使う医療機器といえますが、現在では患者が感じる苦痛も抑えられています。
そこで、ビデオ軟性血管鏡について、特徴や内視鏡検査の方法を簡単に紹介します。
ビデオ軟性血管鏡とは
ビデオ軟性血管鏡は、静脈や動脈の管腔を観察・診断・治療するための内視鏡です。
柔らかく、屈曲が自由で先端にビデオカメラが装填された管(ファイバー)を体内へ挿入し、レンズでとらえた画像をグラスファイバーで体外の接眼部まで導き、肉眼で観察します。
ビデオ軟性血管鏡の特徴
ビデオ軟性血管鏡の特徴は、シャフトが柔軟で先端に可動性が保たれていることです。
脳室内など、複雑な構造でも挿入しやすい機動性がありますが、画質は硬性鏡よりも劣っています。
そのため、広範囲を観察したいときに適した医療機器といえるでしょう。
内視鏡検査とは
内視鏡検査とは、口・鼻・肛門から、内視鏡(ファイバースコープ)を挿入して体内を直接観察する検査です。
たとえば、食道・胃・大腸などの消化管や、気管・気管支・咽頭・喉頭などの内腔の検査に適しています。
検査を行う目的は、消化管や気管などの部位の病変や性状を直接観察することです。
病変の一部を採取し、顕微鏡で観察して細胞の性格により良性と悪性(癌)を判定します。
内視鏡検査の方法
上部内視鏡検査では、直径9~10mmの内視鏡が使われてきました。
現在は、挿入の際に苦痛を感じにくい直径約5mmの内視鏡も登場しています。
外径が細いため、口だけでなく、鼻からの挿入も可能です。
鼻から挿入する場合は、検査中の会話が可能であり、内視鏡が舌のつけ根を通らず嘔吐感もありません。
検査の方法は、先端にカメラが内蔵されたスコープを、口・鼻・肛門などから挿入します。
異常が見つかったときは、内視鏡に付属する専用器具で組織を採取したり切除したりもできます。
症状がない場合でも、内視鏡検査を行えば、ポリープの早期に発見が可能となり、状態によってはその場で切除も可能です。
将来がん化するケースの予防や、がんの死亡率を大幅に減少させられる検査といえるでしょう。
手術をするよりも痛みは少なく、回復も早いため身体への負担は抑えられます。