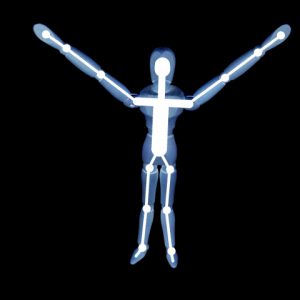循環器内科とは?診療科の特徴や実施する検査の内容を簡単に紹介
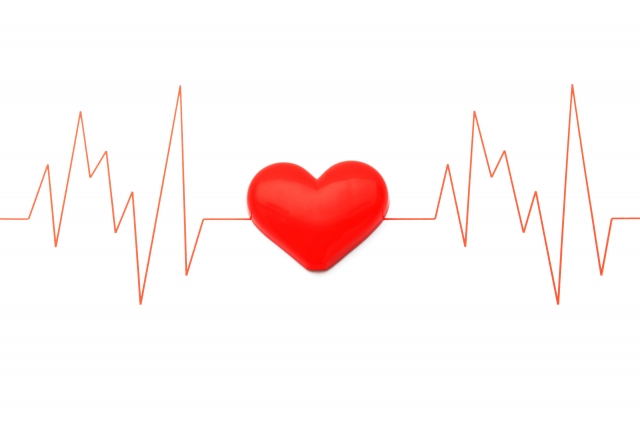
循環器内科とは、心臓や血管などの循環器系を専門とする内科です。
不整脈・心筋梗塞・心臓弁膜症・心筋症・動脈硬化など、様々な循環器系の病気に対する診断や治療を行います。
そこで、循環器内科について、診療科の特徴や実施する検査の内容を簡単に紹介します。
循環器内科とは
循環器内科とは、内科の分野のうちのひとつであり、心臓や血管の病気を専門とした診療科です。
不整脈・心筋梗塞・心筋症・心臓弁膜症・動脈硬化など、いろいろな循環器系の疾患の診断・治療を行います。
心臓は血液を送るポンプの役割を担い、その血液が通るのが血管です。
循環器科では、主に血液の流れに関する病気を扱い、疾患が影響する生活習慣の指導なども含めた総合的な診療を実施します。
循環器内科の検査
循環器内科の検査は、心臓や血管の状態を確認するために行います。
検査と治療を同時並行で実施するものなどを含めて、体の不調をいろいろな角度から確認するため、一般的に以下の検査を実施します。
・心電図
・超音波検査
・心臓カテーテル検査
・心臓CT検査
心電図
心電図とは、心臓の電気活動をグラフで記録したグラフです。
心臓の動きは、電気信号が頭側から足側へ流れることにより起こるため、皮膚に電極をつけて電気信号をキャッチし、波形にして動きを確認します。
体からの電気を受信するため、特にビリビリと刺激などを感じることはありません。
超音波検査
超音波検査とは、エコー検査とも呼ばれ、超音波により体内の臓器や組織の画像を映し出して状態を調べる検査です。
音波を体内に打ち出すことで、反射した音の成分を画像化します。
それにより、リアルタイムの心臓の動きを確認できます。
安全性の高い検査のひとつであり、痛みはなく繰り返し行うことも可能です。
心臓カテーテル検査
心臓カテーテル検査とは、カテーテルを血管から心臓まで進め、心臓や血管を調べる検査です。
脚の付け根にある血管などから、カテーテルと呼ばれる細い管を通し、冠動脈を確認します。
造影剤を入れてX線撮影を行えば、冠動脈が詰まったり狭くなったりする状態を確認できます。
また、狭くなった血管でバルーンを膨らませて、治療を行う場合もあります。
心臓CT検査
心臓CT検査とは、コンピュータ断層撮影(CT) により、心臓や冠動脈の状態を調べる検査です。
比較的短時間で検査を行い、心臓の大きさなどの情報を得られます。